左から順に最新記事です(スマホは右にスクロールできます)
雨のち雨なモヤモヤほけんしつ-CorrEmo
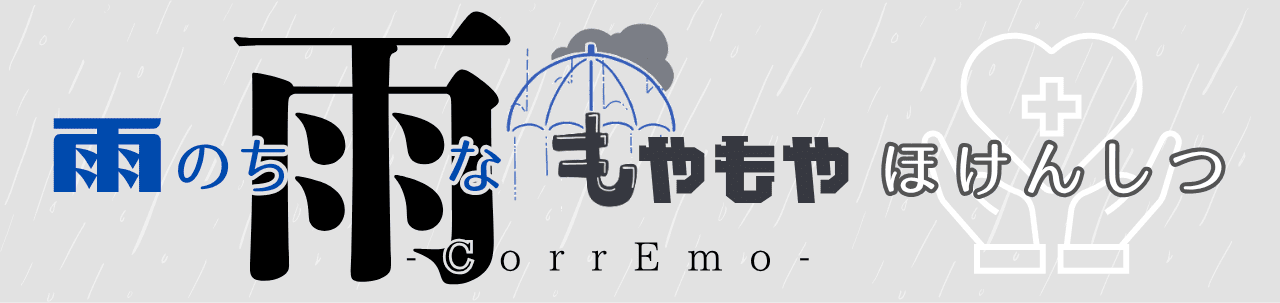
訪問いただきありがとうございます。
人生におけるモヤモヤを自分のせいだと感じる
自分が悪くないはずなのに嫌な気持ちばかりが付きまとう苦しい状況
このような色々な事例を細かく取り上げ、その感情が起こる仕組みを科学的に解説しており、体験談も交えた知識をお伝えしています。
それによって未来の可能性を取り戻したり、自分への攻撃を止められるようになる場です。
心に余裕ができる事で、自分に合った選択肢を見つける気力が沸くような状態へお連れすることがこのブログの目的です。
おしらせ
2025/10/28
現状の活動の方針を別のプラットフォーム主軸にしていきます。
それに伴い、不定期更新とします。
当ブログでの動きが明確になってきた段階で方針を変更する予定です。
こちらで主に活動しています。
note→https://note.com/yasakurest/n/nd1036eb2c566
スタンドFM→『矢沙玖』
2025/9/5
活動の幅を広げるため、2週間に1記事投稿へ変更しました。
2025/6/11
6/10時点で100本目の記事の執筆が投稿されている事を確認できました。
それに伴い、1週間に1記事投稿へ投稿ペースを変更しました。
2025/5/28
ブログ名が迷走していましたが【雨のち雨なモヤモヤほけんしつ-CorrEmo(コレエモ)】に定めました。
『このブログのメッセージ』記事に由来を追記しました。
2025/4/10
全ての記事のリライトが完了し、エビデンスレベルの表記を追加しました。
2025/3/15
お問い合わせフォームが正常に作動しないため、一時的に専用メールアドレスを用意しました。
2025/1/2
記事の投稿ペースを3日に1記事投稿に変更しました。
連絡事項
何から読めばいいか迷う方へ
ショートブログという短い記事をリストアップしています。
どれも1000字前後や2000字前後で2分~5分で読めますよ。
https://yasakurest.net/category/ショートブログ
そして私がどれだけおせっかいをしようとしているのかをまとめた記事
が、こちらになります!
日頃よくある出来事で不安になる気持ちや、心の傷を抱えた体験談を開示し、私の主張と科学的根拠を元に仕組みまで記載し
2024/10/27 設立
「自分の感情は間違っていなかった」
と思えたり
「じゃあこうすればいいのでは?」
が見つかるようなブログを意識しています。
もちろん私もまだまだです。皆様にお届けする過程で学びを深めている最中です。
私と似た経験をお持ちの方には特にお役に立てるかもしれません。
記事で見られるエビデンスレベルについて
エビデンスレベルや記事の生まれ方
エビデンスレベルは何故付けたのか 記事に信憑性があるのか?或いは筆者の経験談や主張なのかを読者の皆様が判断しやすくするためです。 エビデンスレベルは何を表すのか 記事は何か証拠をもって書かれているのかの指標。 または奨められる方法に効能が期待できるのか。その信頼度を表します。 レベルいくつがいいのか エビデンスレベルは1~5の5段階で表記されます。 1:最も信頼できる大規模な研究や専門家の総評 2:信頼できる研究結果で裏付けされたもの 3:観察データや信頼性のある統計を基にした情報 4:専門家の理論的枠組みからくる主張や小規模な研究に基づくもの 5:個人の経験や一般人の経験からくる主張 レベル1がデータの豊富さ的に信用度が高いという事です。 (例えば、いくら経験豊富な人がどれだけ多くを語ろうと、合っている事や上手くいった経験があろうと データの提示、科学的根拠の存在自体が無ければ一般人の主張となり、信頼性がないことになります。 よって、その場合エビデンスレベルは5になります。 根拠の正確さの数字はどうやって出している? この数字はAI(ChatGPT)で情報源の分析を行い、私自身でも実用性やAIの示したものに対し矛盾がないか精査し、その上で決定しています。 読者の皆様にも調べる事ができるよう、根拠となる参考文献の紹介をしており、記事本文中や記事の末に設置しています。 このブログはAI生成記事なのか 違います。 AIは、元となる情報の出典や、私や世間が言う主張に根拠があるか示す際に使われる事があります。 そもそも執筆のテーマは私の経験談や疑問に思ったことがメインであり、それに関係する参考書から得た知識を、私が解釈した通りの言葉で執筆する事が多いです。 そのため、それらの主張が正しいかを精査するためにAIを使用したり、AIが示した参考文献の一部を用いて根拠を補強。これがAIが使われている場面です。 繊細なテーマだからこそ、なおさら間違ったことをお届けしないためです。 エビデンスレベルが低い物は読むに値せず時間の無駄か? エビデンスレベルはあくまでも参考指標であり、信頼性が高くても効果の発揮や事実には個人差があります。 また、低いからと言って効果がなかったり説得力が無いとは限らず、具体的なデータや研究がない場合に低い数字が出ます。

矢沙玖
このブログは記事が100本を超えるまでは3日に1投稿をし、400記事を目指しています。
リライトをする事がありますが、間違った情報や誤字、日本語表現の修正、情報の更新、記事の見易さ改善等、質の向上のために行われます。
どんな事なら約束できるのか?
・こうすれば改善される可能性が高いという事柄の情報提供。
・不安等の感情が起こる仕組みや、特定の現象に対する違和感(なぜパワハラをするのか?等)を解説し、自己嫌悪しない考え方を科学的に正しい方向で掲載。
検索機能で気になるワードを打ち込んでも記事が出てきます。
個人情報の取り扱いに関する取り組みはこちら
お問い合わせはこちら
それでは、ご休息くださいませ。

